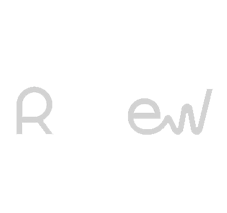日本の再生可能エネルギー市場
最近、再生可能エネルギーにおいて成長を遂げてきた。IRENAの年次報告書によると、2022年末までに太陽光発電は7,880万kW、風力発電は450万kWに達した。この設備容量は、2030年の目標を達成するために、今後数年間で膨大に増加すると予想される。
2011年の福島原発事故は、日本のエネルギー政策に転機をもたらした。この事実は、再生可能エネルギーへの投資をより魅力的なものにする目的で、電力市場の改革を加速させ、自由化し、系統に固定価格買取制度を導入した。
現実には、日本のエネルギー需要を満たすための化石燃料資源は非常に限られており、再生可能エネルギー設備には大きなチャンスがある。
そのため、経済産業省(METI)は、2030年までに36%~38%という目標を掲げた再生可能エネルギー戦略の策定など、クリーンエネルギーの利用を促進するためのさまざまな政策を実施してきた。さらに、日本のグリーン成長戦略報告書によれば、日本は2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目指している。
日本の再生可能エネルギー市場のその他の特徴と課題
- 土地と立地の不足:日本における再生可能エネルギーの可能性は明らかであるが、その発展は日本の限られた山間部の地形、自然災害、高い人口密度によって妨げられている。その困難な地形が、ソーラーパネルや風力発電所を設置するのに十分な土地を見つけることを妨げている。つまり、農業用太陽光発電や洋上風力発電には大きなチャンスがあるということだ。そのため、かつてのゴルフ場やスキーリゾートに太陽光発電所が建設され、1990年代に活況を呈したが現在は使われていないスペースを活用している。 土地の不足に対抗するため、最近では、規模の経済性(ポートフォリオ全体で同じレイアウト、設備、O&M契約)を利用して収益性の高い低圧プロジェクト(1~2MW)のポートフォリオが開発されている。
- グリッドの混雑:日本の地理的な課題に加え、日本には統一されたグリッドがなく、互換性のないグリッドを持つ2つの地域に分かれているため、2つの地域間の送電は不可能である。北部地域(東京から北海道まで)は50Hzで、南部地域(大阪を含む静岡から九州まで)は60Hzで運用されている。 南部地域は日射量が多く、発電所のエネルギー生産量は多いので余剰電力が発生し、需要の多い北部地域(東京)に送電できません。いわゆる「出力制御」が起こり、発電事業者は生産を停止せざるを得なくなる。現政権がこの問題を軽減するために送電網の改良を提案していることです。
- 蓄電池/ストレージ:日本はリチウムイオン電池など、先進的なエネルギー貯蔵技術に多額の投資を行ってきた。日本の複数の企業がすでに、余剰再生可能電力を貯蔵し、供給不足時に放電する能力を備えた、さまざまな大規模リチウムイオンプラントの建設に取り組んでいる。これらの電池は、家庭用、商業用、工業用レベルで使用され、すぐに放電できるため、短期間の蓄電用途に適している。 政府は、蓄電システム(スタンドアローンまたは発電所に接続されたもの)の設置に対する支援・補助制度をまだ定めていないが、出力制御が国内の特定地域に深刻な影響を及ぼしていることから、短期間のうちに決定できると予想される。
- 水素:日本市場は水素研究のパイオニアである。数年にわたる建設を経て、日本の福島水素エネルギー研究施設(FH2R)が2020年3月に稼働を開始した。この施設の目的は、水素プロジェクトの研究実験室として機能し、ガスエネルギー技術の実用化のためのデータを取得することである。この施設は10 MWの水素製造装置で構成され、1時間当たり最大約2,000立方メートルの水素を製造できる。製造された水素は、例えば2021年の東京オリンピックの車両に使用された。 最近、三井物産や双日のような日本企業の船舶を利用した水素の輸入に関して、オーストラリアなどの国々と協力協定を結んでおり、中長期的にはこの種のエネルギーがより重要な意味を持つようになると予想される。
- 洋上風力:洋上風力発電は日本における重要な開発分野である。日本には長い海岸線と深い海域があり、洋上ウィンドファームに適した立地となっている。日本初の大規模洋上ウィンドファームは2022年末に稼動し、2023年4月には、日本の領海を囲む排他的経済水域での浮体式施設の建設を認める新たな法律を盛り込んだ第4次海洋基本計画が承認された。 日本は、主に北方(北海道と東北)に位置するこの種のエネルギーの開発ゾーンを定め、海洋プロジェクトの第3回入札を実施中である。さらに、北海道と本州を結ぶ接続ケーブルの建設が発表され、海洋発電所で生産されたエネルギーを需要の高い地域(首都圏)に送電できるようになる。
- 固定価格買取制度: FIT(Feed-in Tariff)は、再生可能エネルギーを推進し、原子力や石油への依存を減らすためのエネルギー政策の一環として2012年に導入された。この制度は、再生可能エネルギーの長期固定買取価格を設定し、20年間保証するものである。 固定価格買取制度の目的は、より持続可能なエネルギーシステムへの移行を加速させるため、投資家や再生可能エネルギー生産者にこれらの技術への投資を奨励することであった。日本のFITは、日本の再生可能エネルギー導入に好影響をもたらした。導入以来、日本の再生可能エネルギー設備容量、特に太陽光発電と風力発電の設備容量は大幅に増加した。しかし、クリーンエネルギーのコストが高いという批判や、資源利用の効率化の必要性も指摘されている。 日本ではFIT制度が2022年初頭に終了し、それ以降、PPA(電力購入契約)が徐々に電力購入の有効な選択肢となりつつあり、より多くの企業が100%再生可能エネルギー目標を設定するにつれて、大幅な成長が続くと予想されている。直近のPPA契約は最大16円/kWhの評価額に達しており、今後も中長期的に上昇することが予想され、デベロッパーや投資家にとって非常に魅力的なものとなっている。
- 規制: 日本における規制は、再生可能エネルギーの普及に遅れをとってきたが、この分野では確固たる構造を生み出してきた規制の枠組みがある。バイオマス促進法、太陽光発電促進法(1999年)から再生可能エネルギー促進法(2011年)に至るまで、政府は再生可能エネルギー生産者が発電したエネルギーに対して適正な価格を受け取ることができるよう取り組んできた。 このようなシナリオにもかかわらず、日本が新しい送電線を建設し、高度なグリッド管理システムを導入し、分散型再生可能エネルギー発電を促進することによって、市場に対応していることを確認することができる。
2023年、ベクトルリニューアブルズは、状況に適応した市場の成長と発展を目の当たりにして、日本上陸から10年を迎えます。それ以来、ベクトルは日本のお客様に対して、新しい挑戦のたびにサポートしながら、これまでに多くのサービスを提供してきました。
ベクトルは、プロフェッショナリズム、専門知識、そして、起こりうるあらゆる課題への献身を保証し、将来のプロジェクトにおいても同じことを行うことを楽しみにしています。
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
再生可能エネルギーの設置に必要な専門家が見つかります。弊社では世界中で、プロジェクトのライフサイクルを通してサービスを提供しております。必要なデータを入力いただければ、こちらからご連絡いたします。